花コラム
花コラム 第53回:今年こそ~ロウバイの不思議な力で
2022.01.1 第53回:今年こそ~ロウバイの不思議な力で ロウバイ(蠟梅)は不思議な花です。種々の花が咲き乱れる季節は目立たない花木=写真=で、気を引くことは殆どありません。ところが、1月のこえを聞くと俄然、存在感を放ちます。他の花に先がけて、爽やかな香りを漂わせ、半透明のような美しい黄色い花を咲かせて、新しい年の息吹きを運んできます。 ロウバイは高さ2~5mになる落葉広葉樹で、1月から2月にかけて花をつけます。中国ではウメ、スイセン、サザンカとともに、冬を彩る貴重な花として「雪中の四友」と呼ばれ、文人画に好んで描かれています。日本には江戸時代に渡来しました。 名前は、旧暦の臘月(ろうげつ)・12月にウメのような形の花を咲かせ、ウメのような強い香りを放つことに由来するという説があります。しかし、ウメはバラ科バラ属、ロウバイはロウバイ科ロウバイ属で、分類学的には違うものです。 ロウバイを詠った俳句や短歌は数えきれないほどあります。有名なところでは…。 夏目漱石の「永日小品」の中の「懸物(かかりもの)」にもロウバイが登場します。 花言葉は「慈しみ」「ゆかしさ」。花の少ない季節に、うつむき加減に花を咲かせることにちなみます。さらに「先導」「先見」。他の花より一足早く開花することからの連想でしょう。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム

雪中の四花

蝋(ろう)細工?あるいは蜜蝋?
この他、花が蝋(ろう)細工のようだから。さらには、花弁がミツバチの作る蜜蝋(みつろう)のような光沢、質感をしているからーとも言われていますが、花を見ていると、どの説にも頷いてしまいます。文人の愛した花

《蠟梅や雪うち透(す)かす枝の丈(たけ)》(芥川龍之介)
《蠟梅を透けし日射しの行方なし》(後藤比奈央)
《蠟梅の香の一歩づつありそめし》(稲畑汀子)
《蠟梅の老いさびし香のほのぼのとわが枕べを清くあらしむ》(窪田空穂)
文人は、この透き通るような花に美しさ、清々しさ、清らかさを感じ取ったのでしょう。掛け軸の前にロウバイ

《妻に先立たれた老人が石碑を立ててやろうと決心します。お金がないので先祖伝来の大切な掛け軸を好事家に売り、立派な石碑を誂えました。その後、掛け軸が気になり、好事家のところに見せてもらいに行くと、掛け軸は茶室に飾られ、その前には透き通るようなロウバイが活けてありました。老人は「おれが持っているよりも安心かもしれない」と倅(せがれ)に言いました。》
石碑の身代わりとなって売られていった掛け軸は、ロウバイの花が活けられたことによって報われました。ロウバイには、有難い、不思議な力があるようです。コロナ禍の終息を先見
ロウバイは、その有難い、不思議な力と慈しみで「今年こそコロナ禍は終息する」と先見しているーと思いたいものです。◇
「定本 漱石全集」(著者:夏目金之助、発行所:岩波書店)
「花をめぐる物語 尾崎左永子の章」(著者:尾崎左永子ら、発行所:かまくら春秋社)
※参考サイト
「みんなの趣味の園芸 NHK出版」
「暦生活 蠟梅」
「歳時記 蠟梅」
「蠟梅の俳句」
「花言葉‐由来」
コメント
 コメントをする
コメントをする
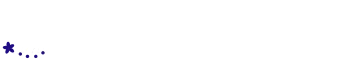
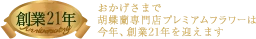
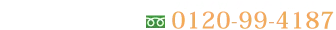
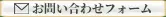
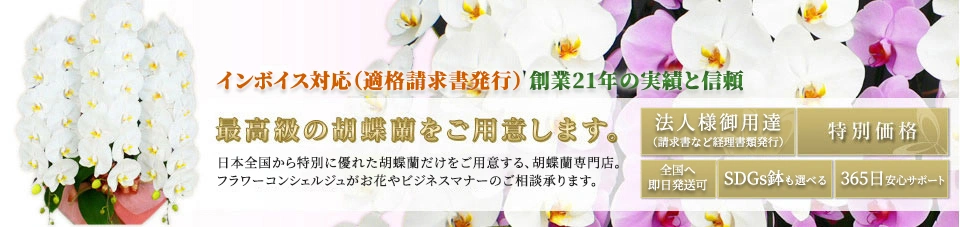
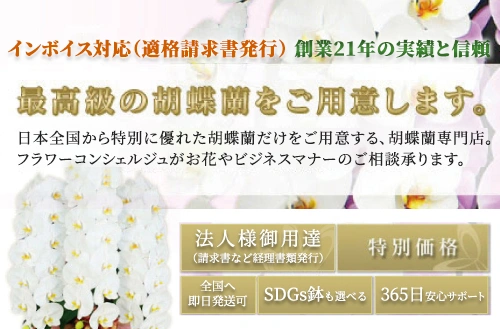


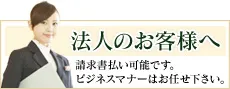

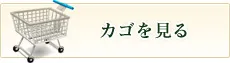
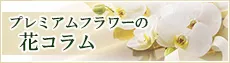
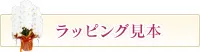


コメントはまだありません。