花コラム
花コラム 第47回:絹のレース編み?それとも“花の骸骨”?~カラスウリ
2021.7.1 第47回:絹のレース編み?それとも“花の骸骨”?~カラスウリ 大概の花は「美しい」「綺麗」「可愛い」などといった好印象の言葉で形容されます。ところが、人によっては印象が大きく変わってくる花もあります。その一つがカラスウリです。 カラスウリはウリ科の多年草で、東北地方の南部から九州にかけて自生しています。7月から9月にかけて開花しますが、その咲き方も花の形もユニークです。 「天災は忘れた頃にやってくる」の言葉を遺した物理学者で随筆家の寺田寅彦(1878~1935)は、カラスウリの生態を著書『からすうりの花と蛾』の中で書いています。 名前の由来は「カラスが実を食べるから『烏ウリ』になった」「生育旺盛なカラスウリが絡みついた木を枯らしてしまうから『枯らすウリ』になった」など諸説があります。 カラスウリは白い花びらを5枚つけます。それぞれの花びらの外側は糸のように裂け、レースを広げたように伸びています。暗闇の中でも、白いカラスウリは目立ち、夜行性のスズメガがやってきて受粉の手助けをします。雌雄異株ですが、同じように花が咲き、見た目では区別はつきにくいそうです。 これだけインパクトのある姿をしている花は、そうは無いでしょう。私は実物を見たことはありませんが、本やネットを見ると、称賛する記述が次ぎ次ぎと出てきます。 ところが、自然科学者の寺田の手にかかると、全く違う表現になります。 寺田は、こうも書いています。 一夜限りの不思議な小宇宙となれば、どうしても見て、自分がどう感じるのかを知りたくなります。カラスウリは日中は目立ちませんが、葉=写真=はハート形で、巻きヒゲが出ているのが特徴です。明るいうちに目星を付けておき、暗くなるのを待って再び見に行こうと算段しています。 ※参考図書プレミアムフラワーの花コラム
夕暮れに開き、翌朝に萎む

《縁側で新聞が読めるか読めないかというくらいの明るさの時刻が開花時で(中略)十分前には一つも開いていなかったのが十分後にはことごとく満開しているのである。実に驚くべき現象である。》
カラスウリは夕暮れ時から日が沈むまでのわずかの間に開花し、翌朝には萎んでしまう一夜花なのです。男嫌いの花、縁起の良い種

花言葉もなかなかユニークです。人目を避けるようにして夜に咲くことから「男嫌い」。きっちりと夜を待って咲くことから「誠実」。さらに、黒褐色の種=写真=が結び文に似ているので「良き便り」。
ちなみに種は、振れば思い通りのものが出てくる「打出の小槌(うちでのこづち)」にも似ています。そこで、財布に入れるとお金が増えるという縁起物になっています。花びらからレースが広がる

美しさを称賛する記述が次ぎ次ぎと
「現実離れしているほど美しい」「神秘的で幻想的な魅力」「青ざめたように白く美しく妖艶」「突然視界に入ってくるとドキッとする」「誰でも綺麗だなあと感嘆の声をあげる」「夏を告げる上品な花」「絹糸のレース編みのよう」…。えっ!花の骸骨?

《花の骸骨(がいこつ)とでもいった感じのするものである。》
えっ!あの骨だらけの骸骨?思わず、読み返しました。カラスウリが気の毒になるようなたとえではありませんか。
寺田は、花びらから伸びた白い糸を骨に見立てたのです。この花が美しいかどうかの概念はなく、何に似ているか、何を連想するかと考えて、見つめたのでしょう。花は不思議な小宇宙
《花というものは植物の枝に偶然に気まぐれにくっついている紙片や糸くずのようなものでは決してない。われわれ人間の浅はかな知恵などでは到底いつまでたってもきわめ尽くせないほど不思議な真言秘密の小宇宙なのである。》
そう言われれば、どうして花びらから白い糸が伸びているのかも分かりません。見て、感じたい

◇
「寺田寅彦随筆集第三巻 からすうりの花と蛾」(編者:小宮豊隆、発行所:岩波書店)
「カラスウリのひみつ」(著者:真船和夫、発行所:偕成社)
「朝に咲く花・夕に咲く花」(著者:南光重毅、発行所:誠文堂新光社)
※参考サイト
「花言葉⁻由来」
「草木図譜」
「カラスウリ‐松江の花図鑑」
「カラスウリ‐徳島県立博物館」
コメント
 コメントをする
コメントをする
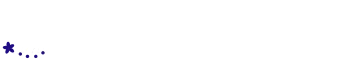
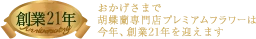
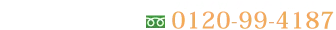
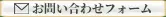
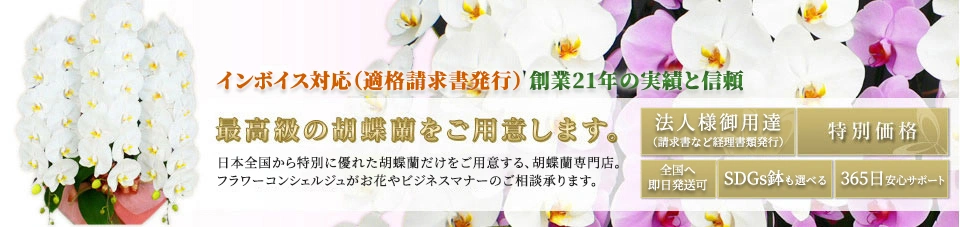
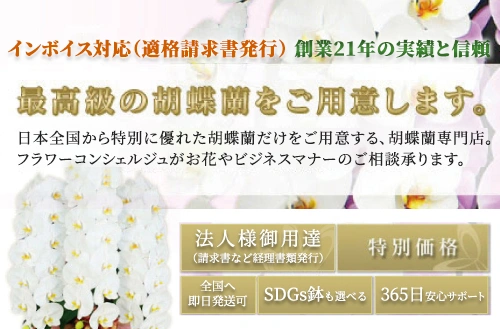


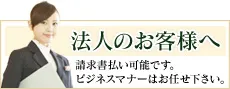

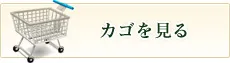
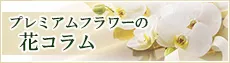
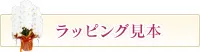


コメントはまだありません。