花コラム
花コラム 第2回:眺めて愛で、食して愛でる阿房宮
2017.10.04 第2回:眺めて愛で、食して愛でる阿房宮 花の名前の由来には、はっきりしないものが数多くあります。例えば、食用菊の『阿房宮(あぼうきゅう)』。秦の始皇帝(紀元前259~210)が70万人を動員して造営したといわれる巨大な宮殿の名前が、どうして花につけられたのでしょうか? 相内では、どの畑にも必ずと言っていいほど鮮やかな黄色い一角がありました。1mほどの茎の先端に直径が10~15cmの大輪がびっしりと咲く様は、遠目にはまるで黄色い絨毯。阿房宮は800年ほど前に、南部藩主が京都の九条家から株分けしてもらい、相内に植えたと言われています。 10月から11月いっぱいにかけて、この阿房宮が様々な料理になって、青森の食卓をにぎわします。 おひたしや味噌汁の具、天ぷら‥‥。地元でご馳走になった菊づくしの料理は、油で揚げても、酢であえてもシャキシャキとした歯触りで、ほのかな甘みがありました。宿で熱燗に花びらを浮かべて飲むと、柔らかいのど越しと芳醇な香りがし、「風流だなぁ」と一人悦に入ったものです。 =写真は青森県観光企画課提供= ◇ 食用菊は約60種類もあります。山形県産の紫色の大輪種は『もってのほか』。名前の由来は「天皇家の家紋である菊を食べるのは、もってのほか」と「もってのほか美味しい」という二つの説があります。プレミアムフラワーの花コラム
見事な大輪を宮殿になぞらえたか?それとも、甘い香りが、宮廷にはべったという美女三千人を連想させたのか?そんな疑問を抱きながら、阿房宮の本場・青森県南東部の南部町相内(あいない)を訪れました。相内と相性がいい花

青森でも日本海側の津軽地方は米どころとして知られていますが、太平洋側の南部地方は冷たい北東の風・ヤマセが吹きつけるので、米作だけでは生計を立てられません。そこで、相内の農家は畑作を必死で手掛けたのでしょう。それになぜか、阿房宮は他の地で育てると、なかなか甘くなりません。阿房宮は相内と相性の良い花だったのです。南部女性のような花

「阿房宮は南部の女性のようなもんだなす」。地元の郷土料理研究家の沼畑澄さんは面白い例え方をしました。日本料理だけでなく、西洋・中華料理にも合う。そして、合わせながらも、菊独特の香りは失わない。厳しい自然に順応して生きながらもなお、自分らしさを失わない。その優しくて芯の強いところが、南部女性に通じるというのです。独特の歯触りとほのかな甘み

花を眺めて愛でるだけでなく、花びらを食しても愛でる。阿房宮はなんと贅沢な花なのでしょうか。そう考えると、贅を尽くして建てた宮殿・阿房宮が花の名前になったのも頷けるような気がしました。
コメント
 コメントをする
コメントをする
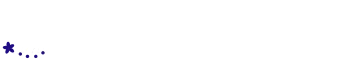
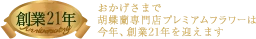
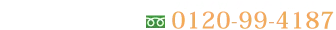
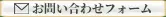
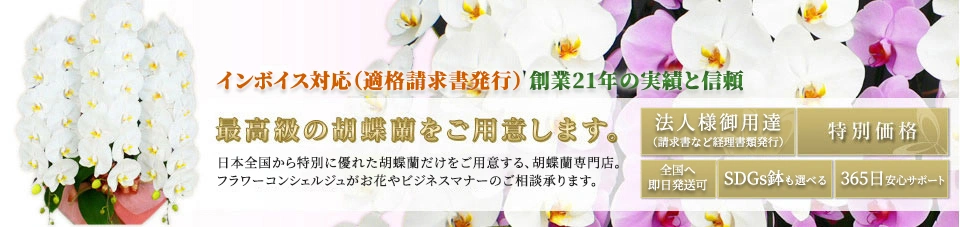
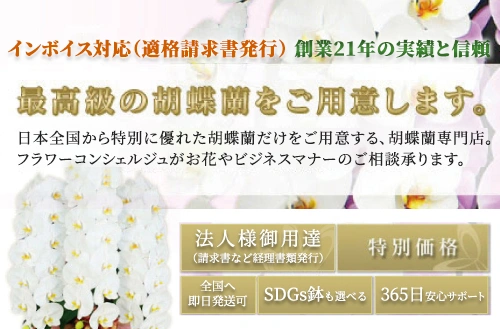


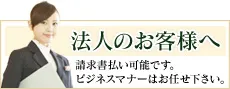

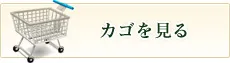
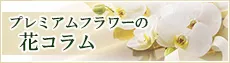
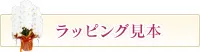


コメントはまだありません。