花コラム
花コラム 第1回:花と生きる - ハマギク -
プレミアムフラワーの花コラム
2017.9.4
第1回:花と生きる - ハマギク -
30数年間の新聞記者生活で、大小合わせると1万本近くの記事を書いてきたでしょうか。社会一般、政治、話題、事件、事故‥‥。内容は多岐にわたりますが、中でも『花と生きる』と題した紀行文の連載の取材は思い出深く、スクラップ帳を開くと、景色までもが蘇ってくるようです。
ひな祭りの餅を取りに戻って‥‥
入り江と断崖絶壁が続く岩手・陸中海岸の中ほど。取材で訪れた田老町(現・宮古市田老地区)の海は不気味なほど静まり返り、ウミネコの鳴き声だけがやけに大きく響いていました。
昭和8年3月、この地に大津波が押し寄せました。8歳だった田畑ヨシさんはいち早く一家そろって裏山に逃げましたが、お母さんは「子供たちがひもじい思いをしないように」とひな祭りの餅を取りに戻って、帰らぬ人となりました。
ハマギクは咲いた

津波が何もかも奪い去ったその年の秋。田老海岸の岩場にハマギクが何事もなかったかのように白い可憐な花をつけたのを、田畑さんは鮮明に覚えています。白い花の中に黄色い小さな筒状花が密集する直径6cmほどの多年草で、真冬の風雪にも、津波にも耐える強い生命力を持った花です。
日本一の防浪堤
村を捨てて津波から逃げるか、この地にとどまり厳しい自然にハマギクのように立ち向かうか。二つに一つを迫られた村人はとどまる道を選び、田老町に高さ10m、長さ2?以上の日本一巨大な防浪堤を44年の月日をかけて作りました。そして、田畑さんは自身の体験をもとに紙芝居「つなみ」を制作し、「津波てんでんこ(津波が来たら、てんでんバラバラに高台に逃げろ)」と子供らに語り継ぎ続けました。
二度目の大津波
「海に奪われるものも多いんだが、海から与えられるものも多ごぜんす。ここでは、ハマギクのように、海と一緒に暮らすしかねえからねんす」。“津波の語り部”となった田畑さんの穏やかな語り口が忘れられません。
この取材から20数年後、東日本大震災が発生し、大津波は“万里の長城”と呼ばれた、あの巨大な防浪堤をも乗り越えて、再び田老町を襲いました。田畑さんにとっては、二度目の大津波です。田畑さんのお宅は流されましたが、田畑さんは自ら「津波てんでんこ」を実践し、ご無事だったと人づてにお聞きしました。
今年の秋も

大震災から6年が経ちました。田老町の様子はすっかり変わりましたが、ウミネコが舞う田老海岸ではこの秋も、ハマギクは可憐な花をつけることでしょう。
◇
私たちは誰もが花とともに生きています。このコラムでは、そんな日々の光景を折に触れて綴ります。
コメント
 コメントをする
コメントをする
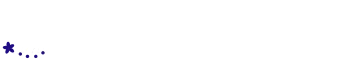
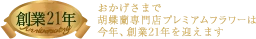
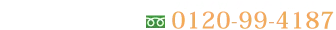
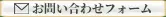
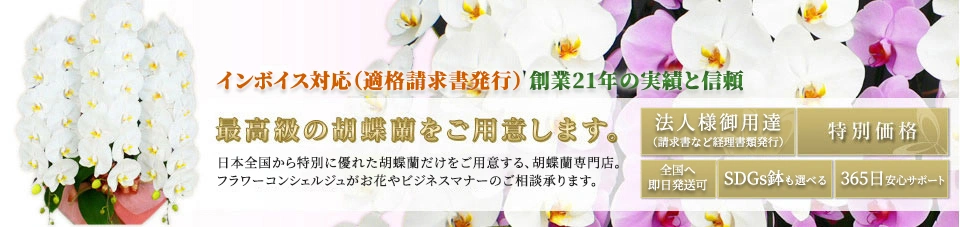
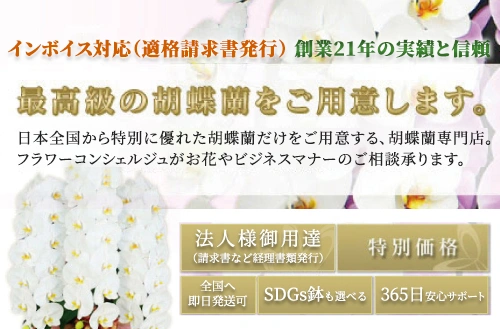


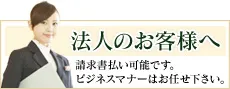

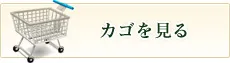
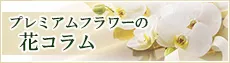
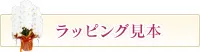


コメントはまだありません。